この記事では、代表的な資産の一つである債券の長期的な目線で解説する。長期的な視点で、債券は、株式よりも富を増加させる効果は少ないが、増加させることは出来る。
債券とは
ものすごく簡単な説明では、借金という言い方ができる。債券は、その発行体がどこであるか?ということで、リスクが大きく違います。例えば、倒産しかけている会社の債券は、その会社が倒産してしまえば、発行体が無くなったため、紙きれになります。これは、もちろん株式も同じで、保有している株式の会社が倒産すれば、株式の価値も0になります。債券の場合は、発行体が国や地方自治体とうケースも珍しくありません。いわゆる国債や公債というものです。ちなみに、米国の国債の名前は、トレジャリーと呼ばれます。もちろん、国際や公債は、会社が発行する社債と比べて、かなり安心感はありますが、2011年には、ギリシャの国債が債務不履行(デフォルト)になっているので、絶対に安心できる資産であるということも出来ません。基本的には、債券の有効期限が長いほど、利子が大きくなるという特徴があります。長い期間資金が動かせないため、なるべく沢山お金を払うので、借金させて下さいということですね。
債券は、借金に対して数パーセントの利子を支払うことで、もともと預けてもらったお金よりも多くのお金を貸主に返す、すなわち現金で現金を増やすという仕組みで富を増やすことが出来ます。借金は我々の生活の周りでも沢山あるので、理解しやすいですよね。借りる側にならないようにしたいものです。細かい話ですが、米国債の場合は、購入するときに、割引で購入できて、満期まで保有すると割引が無くなった元の額の現金を返すという制度の債券(ゼロクーポン債)もあります。この現金で現金を増やす仕組みであるということが、債券の難しいところでもあります。現金は、もともと時間が経てばたつほど、価値が減少する性質があります。そのため、価値が減少する現金に対して、現金を増やす仕組みの債券は、現金の価値が減少するよりも沢山の利子をもらえなければ、富を増やすことができません。経済の用語で表現すると、インフレーションよりも債券利回りの方が高くなければ、富が増えていないのと同じです。この現金で現金を増やす仕組みは、銀行預金も同じです。債券よりも利子がすくないので、銀行預金は、長期で保有すると富が減少してしまう可能性があります。最近、明治時代に発行された100年貯金のニュースがありました。概要は、当時1円を預けて、100年後に1万円になるという金融商品でした。当時の1円は、今の5000円位の価値があったため、当時の1万円は、5000万円の価値があると考えられました。ちなみに、利子は年間10%位でした。貯金がインフレ負けしていることを象徴するニュースですよね。
利子が高い債券は価値が0になる可能性がある
お金の価値の減少よりも利子で増加する分の方が多くなければ、債券を購入する意味はありません。一方で、利子が高い債券は、債務不履行(デフォルト)すなわち債券が0円になる可能性あります。すなわちなんでもかんでも利子が高い債券を購入すればいいという訳ではありません。リスクとリターンのバランスが大切になってきます。とはいえ、20年や30年といった長期間にわたる債券は、無いので、実際は、2、3年の満期の債券を購入して満期まで保有して利子を受け取って、また利子と元本分を別の債券を購入して、満期まで保有してということを繰り返すことになります。これがとっても大変なので、世の中には、債券ファンドというものがあります。債券ファンドは、ファンドマネージャーがお客の代わりに、上述した方法で預かった現金を増やしてくれるというものです(沢山の債券を同時に何個も買ってくれているので、一つの債券を保有している場合よりもリスクは下がります)。ただ、手数料が取られて実際の富の増加分は、自分でやりくりした場合よりも低くなってしまいます。
金と株式と債券の比較
債券としては、ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF (AGG)というファンドの結果を見てみます。米国内の債券をファンドマネージャーが運用している代表的な証券です。見られるチャートは2015年からなので、2015年と2025年のファンドの価値を見てみます。2015年は、112 ポイントで、2025年は98 ポイント位で、実は債券の価値は、この10年で下がっています。金の価値は、チャート(https://www.rakuten-sec.co.jp/web/fop/commodity/lineup/gold_long_chart/)から、2015年で、1200 ポイントで2025年で2600ポイントで、2.16倍です。この時点で、金に負けていますので、実質的な富の増加は、この期間においては出来ないということが分かりました。インフレ負けしているということです。当然、株式には利回りで負けています。例では、インフレ負けしていましたが、もちろん、インフレに勝っている期間があるのが普通です。ただ全体感としては、株式よりも利回りは低くなります。では、いいとこないのか?という話ですが、2年とか3年とかという短期的には、満期が来れば確実に富が増えるので、2、3年の後に使う現金の準備としては、株式よりも有利です(株式は価格変動が大きいので)。また、株価の暴落が起こったときには、債券の価値が相対的に上がるため、その場合は有利だというのが通説です。
まとめ
債券は、長期的には株式よりは、富を増加させる機能が小さいです。一方で、2,3年という短期(満期まで保有すれば)確実に、現金を増加させることが可能です。しかし、債券の発行体は、よくよく選ぶ必要があります。本サイトでは、他にもお金に関する記事を書いているので、そちらも参考にしてみて下さい。

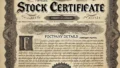

コメント