社会生活を行っていく上で、敏感かそうじゃないかということは、どれくらいストレスを貯めずに生活できるかという観点で重要である。この記事では、敏感な人とそうじゃない人の違いについて説明する。
メルカリ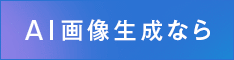
敏感さとは?
人間は、生きていると外界から色々な情報が入ってきます。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚と人間の5感全てから情報が入ってくることになります。これらの情報は、無意識によって、情報を取捨選択していると考えられています。無意識が必要な情報と分類すれば、その情報は、意識に上がってくることになります。
この時、より多くの情報を意識に上げる人がいます。この違いは、単なる脳の機能の志向の違いです。人間の脳は、意識に上がってきた情報を、意味づけしようと頑張ります。この時の脳にかかる負担は、無意識から意識に情報が上がってくる量が多い人よりも少ない人の方が少なくなります。いわゆる敏感な人とは、この無意識の選別によって、より多くの情報が意識に上がってくる志向が強い人です。敏感さとは、いい悪いではなく、単なる脳の使い方の癖の違いです。より沢山の情報を意識出来る方が、生存確率が高い場合がありますので、この特性を持つ人の方が有利な状況もあります。一方で、沢山の情報を処理する必要があるため、外界から入ってくる情報が過剰である場合は、ストレスを貯めてしまうということがデメリットになります。
逆に、無意識が意識にあげる情報が少ない人は、その情報処理の負担が少ないので、ストレスを貯めにくくなります。一方で、聞いていても聞けていない、見ていても見えていないのように、身の回りで起こっていることが、認知出来ていないことが発生します。これは、これで社会生活を送る上で、あまりいいことではないでしょう。どちらの脳のタイプでも、一長一短です。結局、どちらのタイプに偏っているのが良いのかということは、言えないというのが結論になります。このことからわかることは、人間には、この意識出来る情報が多い人と少ない人のグラデーションがついているので、みんなが協力して生きていくというのが、世の中をよりよくすことにつながるということが分かります。
おわりに
今回の記事では、「敏感さ」という、言葉に注目して、無意識の働きについて説明してみました。この記事がなんで自分はこんなに生きづらいなぁと思う人に届くと嬉しいです。本ブログでは、不登校関連の記事も書いているので、そちらも参考にしてください。



コメント